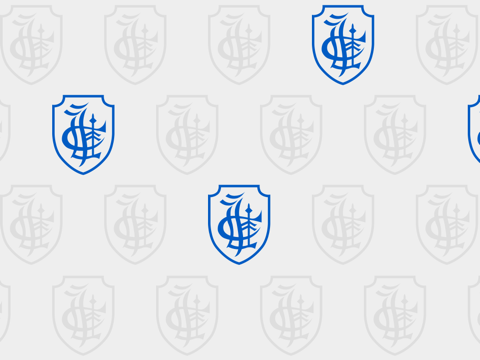2016年9月10日、国際基督教大学・東京大学名誉教授で、日本アスペン研究所副理事長の村上陽一郎先生による講演会「ヒトから人間へ —本能から自由になった人間—」が、東京・内幸町の日本プレスセンタービルで開催されました。
-------------------
この講演会はICU同窓会主催の「リベラルアーツ公開講座」の第2回として開かれたもので、今回は大学が協賛。211人が参加して熱心に耳を傾けました。
村上先生は1936年、東京生まれで、専攻は科学史、科学哲学、科学技術社会論。講演で先生は、前回の講演の中心テーマだった「リベラルアーツ」の重要性にさかのぼって話をスタート。「リベラルアーツ」における「教養」は、「自分が生きてきたのとは違う世界に自分の心を開いていく」ということのほかに、「自分の中に何かを確立する」という意味合いがあり、後者の意味での「教養」は、英語のカルチャーよりも、ビルドゥングスローマン(教養小説)などで使われるドイツ語のビルドゥングス(自己形成)が近いと述べました。
そのうえで、「ヒト」が、一人の「人間」としてつくられていくプロセスを問いかけ、スイスの動物学者アドルフ・ポルトマン(1897~1982)の「生理的早産」という言葉を紹介しながら、熊や馬などの大型動物は生まれてすぐ立ち上がるのに対して、生物学的な種としての「ヒト」の赤ちゃんは、直立二足歩行もできないうえ、コミュニケーション能力も備わっておらず、いわば、未成熟のままに生まれるというのがその基礎的な特徴であると指摘しました。
いわば「早産」した「ヒト」は、「第二の子宮」とも呼ぶべき母親(役)との関係の中で言語によるコミュニケーションを学び、それによって、感覚的な世界の分け方(分節化)を身に着ける一方、そのプロセスの中で「規矩(きく)」とも言うべき、価値観や行動様式も学びとっていくと語りました。
こうした「ヒト」を動物と比較した場合、「ヒト」は「食欲」「戦争などの殺戮欲」「性欲」などの面で、動物には本来的に備わっている抑制機構が脆弱で、その欲望を抑制する装置として共同体の秩序である「ノモス」がある一方、個人は共同体のノモスを全面的に受け入れるわけではなく、変化と創造の基であり、発展のエネルギーとも言うべき「カオス」を抱えていると指摘。社会の「中心」は、ノモスに好意的な個人が占める一方で、「周縁」では、ノモスへ反逆する人が占め、後者の典型が宗教家や近代社会における芸術家であると語りました。
そして、『チャタレイ夫人の恋人』を翻訳し、わいせつ物頒布罪に問われた作家の伊藤整と版元をめぐる裁判で新聞の見出しとなった「芸術か猥褻か」という言葉で分かるように、「芸術」であれば、社会を壊すような表現であっても許される、つまり、「芸術」の中では「カオス」は寛大に扱われることになると述べたうえで、「近代芸術は、社会が生み出したカオスのエネルギーを吸収するための装置ではないか」と語りかけ、講演を結びました。
(記事:鷲見徹也、13期、写真: 滝沢貴大、62期 ID18)
▼ 講演中の村上先生(上) 会場風景(下)